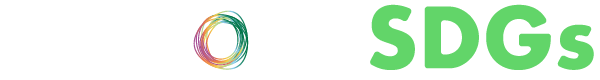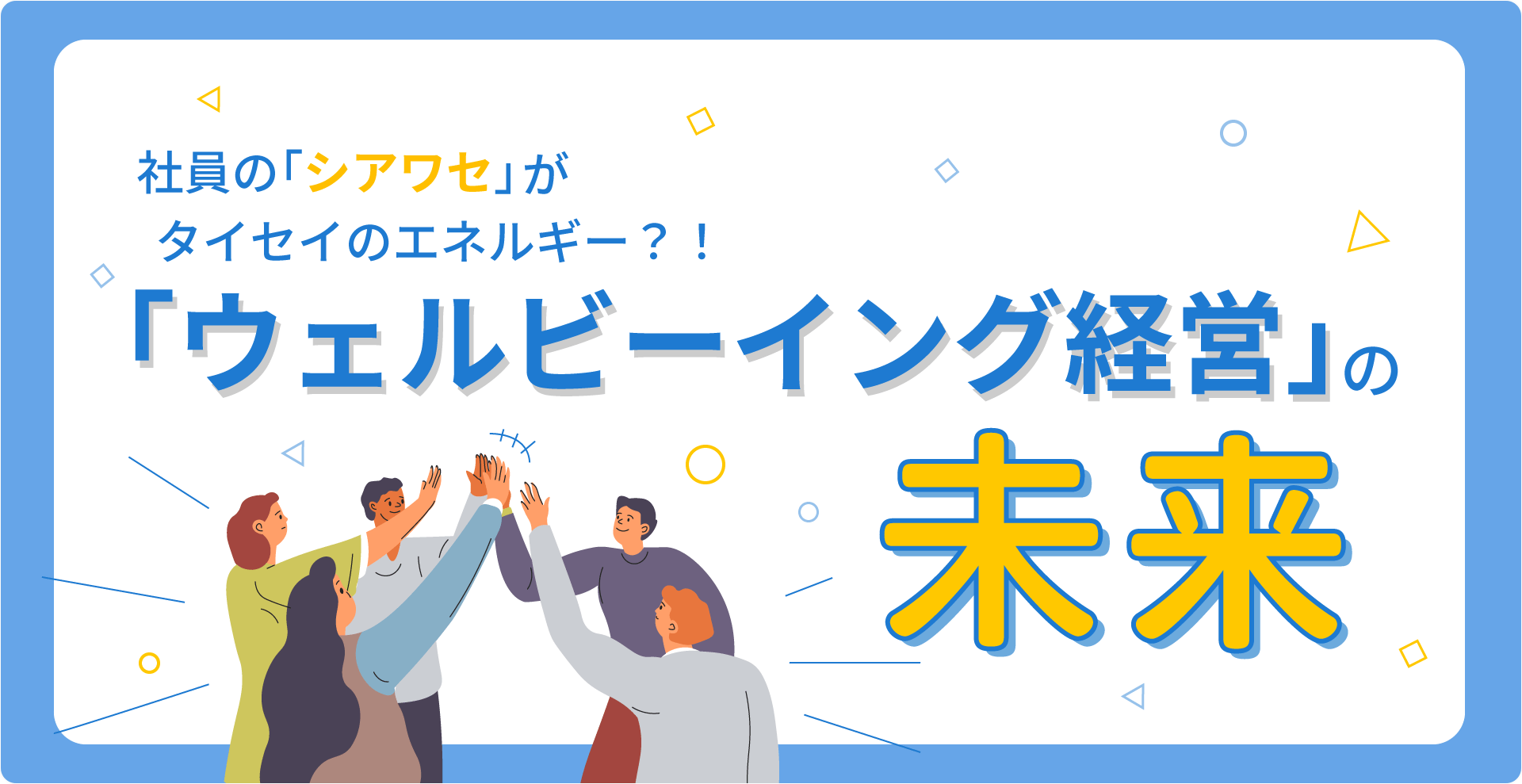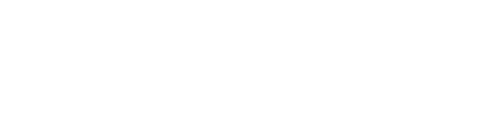育休は制度から文化へ。大成の子育て環境を、育休経験者が本音で語る
2025年4月1日、育児・介護休業法の改正がおこなわれ、仕事と育児・介護を両立できる環境づくりのためにさまざまな制度が整備・拡充されました。とくに、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充は、雇用環境改善の観点から大きな注目を集めています。
大成は長年、社員の育休取得を推奨しており、本メディアでも、育休経験者へのインタビューをおこなってきました。2025年4月からは短時間勤務対象範囲を中学校就学までに拡大し、子どもをもつメンバーが働きやすい環境づくりをさらに強化しました。
さまざまな取り組みの結果、育休取得率は96%に達し、男性の育休取得率も100%(女性94%)、育休復帰率77%と複数の指標で高水準をキープしています。最初は単なる制度に過ぎなかった育休関連のルールも、今や社内では当たり前となり、大成社員の誰もが自然に享受する「文化」になりつつあります。
今回は、実際に育休を取得した3名に話を伺いました。子育てと仕事の「ワークライフバランス」を前提とする大成の文化を紐解きます。

性別に関わらず、育休取得は「当たり前」
——産休・育休について最初に相談したのは誰だったのでしょうか?
駒崎:私は妊娠がわかってすぐ、所属部署の担当役員だった社長に相談しました。安定期に入るまではオープンにしたくなく、その相談も兼ねて社長に連絡を入れました。
相談した際の第一声は「おめでとう!」でした。社長は「家庭第一、家の中が安定してはじめて仕事に注力できる」という考え方で、私が長期休暇をとることにまったく困った様子はなく、むしろしっかり休んでほしいと後押ししてくれました。
その後、管理職も含めた場であらためて社長から「こま(駒崎)がいなくなることは、部署の成長につながるチャンスだ、戻ってくるころにはステージが一つ上がっていることを目指そう」とポジティブな言葉をかけてくれたこともよく覚えています。

木田:私は2回育休を取得しており、どちらもそのときの上司に相談をしました。リアクションは両方ともアッサリで「そうかわかった」といった言葉が第一声だったと思います。「育休はとって当然」という雰囲気で、すぐに取得のタイミングや長さの相談になりました。
私が1回目の育休をとったタイミングはちょうど「産後パパ育休」が新設された時期でした。当時39歳だった私は、「自分が制度を活用すれば、後輩も使いやすくなるかな」と思い、育休取得を決めました。
「産後パパ育休」:産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度

島田:私は育休取得の直前で異動があり、異動後すぐに新しい上司に相談をしました。「そうだったのね!おめでとう」と言われたのを覚えています。その後は木田さんと同じで、必要な手続きの相談に進みました。
実は育休をとるか迷っていて、木田さんにも相談をしたことがあります。木田さんの「先輩が育休をとらなければ、後輩がとりづらくなるかもしれない」という考えを知り、自分も後輩のためにとった方がいいかなと思い、最終的には育休取得を決めました。

各種制度をうまく活用し、柔軟な働き方を実現
——ご家族が増えるにあたって、会社からのサポートは何かありましたか?
木田:私にとっては働き方に関する制度が整っていたことが何よりのサポートでした。
私のパートナーは1回目も2回目もつわりがひどく、体調不良は出産まで続きました。パートナーを支えるため、育休前からしばらくの間は朝7時に出勤して16時にはなるべく退社するようにしていました。家でご飯をつくって、子どもをお風呂に入れるためです。
また、パートナーが病院に行くときは、私が上の子の面倒を見るために半休を取得することもありました。そのような生活ができたのは、フレックスタイムや時差出勤、半休などの制度が整っていたからです。
駒崎:私も柔軟な制度に助けられ、とくにリモートワークの頻度を増やせたことは助かりました。
システム部門という特性もあって、元々週の半分は在宅という働き方でしたが、つわりがひどい時期は、週5日フルリモートで働いていました。あまりよくないですが、ベッドで横になりながらイヤホンだけで打ち合わせに参加できたことは、当時の私からすると非常にありがたかったです。(笑)

——駒崎さんの場合は1年以上のお休みでした、引き継ぎは大変ではなかったでしょうか?
駒崎:まったく問題ありませんでした。いつ誰が休んでもいいような組織体制になっており、後任に引き継いだのはチームメンバーとの1on1ぐらいです。
各システムやプロジェクトには必ずメイン担当とサブ担当を配置し、他のメンバーにも社内チャットや議事録で進捗を共有していました。私が抜けるときは担当プロジェクトに別のメンバーがアサインされ、それでおしまいです。とくに業務が滞ることはありませんでした。
育児と仕事の両立が「自由な働き方」につながる
——育休後の子育てと仕事の両立の仕方を教えてください。
木田:業務時間はなるべく定時におさめ、子どもが体調を崩した際は休みをとるようにしています。また、パートナーからの頼まれごとも積極的に引き受け、仕事に支障が出る場合はメンバーと相談してなんとか調整するようにしています。
私は昔から、仕事を理由に家事や子育てをおろそかにしないように心がけてきました。育休で2〜3か月休みをとったからといって、子どもの手間がかからなくなったわけではありません。育休取得後は仕事モードではなく、むしろ子育ての本番ととらえています。
上司や周りのメンバーにも助けてもらいながら、育児と仕事の両立を目指しています。
駒崎:私は復帰後、出社頻度を減らしてリモートメインで仕事をしています。産休・育休前は週の半分は出社をしていましたが、今は週1〜2回しか出社していません。
子どもが体調不良で預けられない日は、子どもの就寝後に仕事をするなど臨機応変に仕事をしています。柔軟な働き方を許容してもらえていて、会社には本当に感謝しかありません。
迷惑をかける部分も大きいと思いますが、とあるメンバーの「駒崎さんがワーママになってくれて良かった」という言葉に救われました。子育てしながら働いている人が近くにいることで、キャリアの選択肢が広がるとのことでした。私の存在を受け入れてもらえたような気がして、うれしかったです。
——産休・育休をとって、考え方に変化はありましたか?
駒崎:子育てもマネジメントも同じだと思うようになりました。
私とパートナーという限られたメンバーのなかで、24時間をどう過ごすのか。家庭というシステムの効率的な運営と、子どもの育成をどうやって実現させるか。追求するほどチームマネジメントとの共通点が見え、復帰後にも育休中に培った知見やスキルが活用できています。
産休・育休の間は、キャリアにとっては停滞だと思う女性は多いです。しかし私は、考え方次第ではキャリアアップにもつながると感じています。
加えて、育児と仕事の両立は、場所や時間に縛られず働く訓練にもなります。そう考えれば、産休・育休の取得は必ずしもキャリアにとってマイナスではないと思います。
誰でも理想のキャリアが歩める大成を目指して
——今後の展望を教えてください。
駒崎:まずはIT戦略推進室として掲げる、デジタル活用・DXに関する目標達成を目指します。合わせて、デジタル・AIの利活用を促進するための、教育体制や学習プログラムの開発・運営にも取り組みたいです。
そのためにも、さらなるキャリアアップを目指すつもりです。実力を身につけ、理想を実現させたいです。
島田:私も将来的には現場社員の教育に携わりたいと思っています。ちょうど今、組織体制の変更があり、比較的縦割りだった体制から、よりフラットな体制へと変わりました。他チームのいいところを吸収しつつ、現場スタッフに自分の学びを還元し、サービス品質の向上に貢献できればと考えています。
そのためにも駒崎さんと同じですが、自分自身の発言力を高めるために、キャリアアップを目指します。とくに私は現場出身の社員であり、私が活躍すれば後輩の選択肢を増やすことにもつながるはずです。
自身の居場所を自分でつくり、結果的に誰かの居場所をつくることにもつながればいいなと思っています。

木田:私は、今よりもさらに男性が育休をとりやすい環境づくりに貢献したいです。島田さんだけでなく、他のメンバーにも私の経験を伝えられればと考えています。
育休は誰でもとれるし、決して大変ではありません。大成での育休取得が今よりもさらに当たり前になるよう、私にできる貢献を続けたいです。